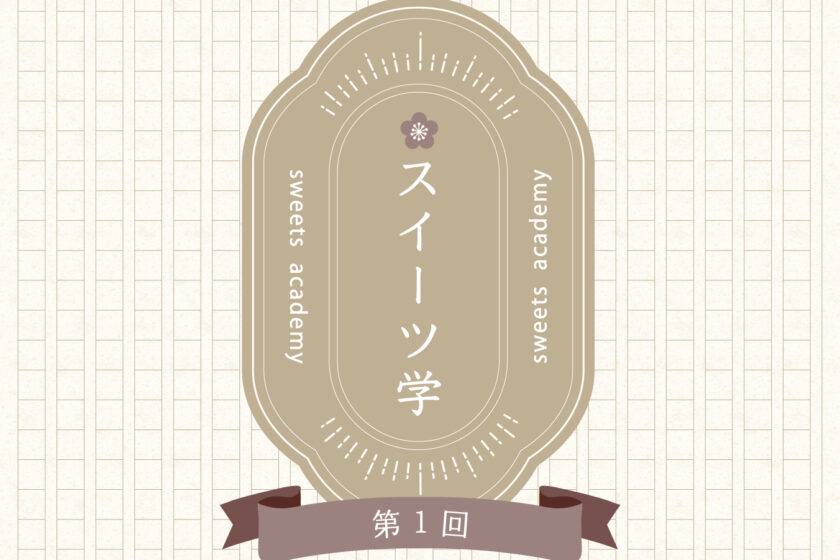長引くコロナウイルスの影響により、多くの産業が打撃を受けている中で、街の洋菓子屋さんからは「売上がアップしている」という話を耳にすることも多く、元気をもらっています。そうした話を聞くと、「やはり洋菓子は生活文化産業だ」と思うのです。
明治の開国に端を発した日本の洋菓子産業は、150年以上の歴史がありますが、そのうち半分は、一部の富裕層の人たちのものだった時代。一般の人たちも楽しむことができるようになったのは、戦後の高度経済成長期以降の技術や情報の発展に伴ってです。特にこの30年の劇的な変化を少し振り返り、整理しておきたいと思います。
ポイントは3つ。
ポイント1は、コンビニスイーツの出現です。
街のケーキ屋さんの中には、パイ(お菓子というものを求めるお客さん)の取り合いとなるという人もいれば、洋菓子店のお菓子とコンビニスイーツとは全く異なるので気にしないという人もいました。
コンビニスイーツの出現は2009年、バブル景気もはじけ、デフレからの影響で、消費者は高級路線のセカンドラインを求めるようになっていた時代でした。全国に販路を持つコンビニエンスストアは、消費者に応えるかのように、洋菓子店に引けを取らない高品質、その割には低価格設定である洋菓子を提供したのです。
すでに洋菓子店により形成されていたファッション的要素もあり、高級感もある洋菓子は消費者にとってはプチ贅沢を楽しむ格好の商品となりました。反対に、コンビニスイーツはジュースや弁当のついでに甘いものを買う「ついで買い」ができる商品、洋菓子店ではケーキ1個だけでは買いにくいが、コンビニなら気にせず買うことができるという「手軽な」商品となっていったのです。
ポイント2は、お菓子の種類です。
高度経済成長期から街の洋菓子屋さんのショーケースには、シュークリーム、プリン、モンブラン、ロールケーキ、チョコレートケーキ、苺のショートケーキ、チーズケーキが並んでいました。今でも街の洋菓子屋さんの定番菓子です。
ところが、1990年代、街の洋菓子店舗には、バブル時代の寵児といわれているイタリア菓子のティラミス、クレーム・ブリュレをはじめ、タピオカ、ナタ・デ・ココ、パンナ・コッタ、カヌレ、ベルギーワッフル、クイニーアマン、エッグタルト、マカロン、生キャラメルなどが毎年次々と流行をうちだしていきました。
さまざまな国や地域性のある、五感に訴えるサプライズ感満載のお菓子でした。こうしたお菓子の拡散は食べた人が口コミで伝えていったのです。
つまりポイント3は情報発信です。
口コミは、店舗側は広告にコストをかけずに情報が拡散できるメリットがあります。一方、消費者側はお菓子を通じて共感を得たり、評価をしてもらえるというメリットがあります。
お菓子により発見や感動といったサプライズのツボが押されたら、誰かに伝えたい、共感してもらいたいという心理が働きます。同じ感性を持った人がその情報を得ると、自分より先に情報をキャッチしていた人のセンスの良さを評価するでしょう。そして、また自分も口コミを行うのです。そうした視点から見ると、口コミは店舗側と消費者側双方の何か信頼関係のようなものから生まれてきた機能だとわかります。
さて、ここ10年足らずの洋菓子業界はどうでしょうか。一層発展した情報や技術、それに伴う消費者の意識や動向にどのように対応しているでしょうか。
コンビニスイーツがお手本にしていた街の洋菓子店を、今は街の洋菓子店がコンビニスイーツをお手本にしていませんか。消費者を流行という波にしっかりのせていたサプライズ感満載の新種のお菓子は、今では既存のお菓子の第2次●●、第3次●●になっても仕方がないとあきらめてはいませんか。承認欲求の高いSNSに依存した消費者に店舗側は踊らされたりはしていないでしょうか。
洋菓子産業は生活文化産業としてこれまで幾度となく業界を取り巻く環境の変化にさらされてきています。そのたびにしなやかに対応し、一層の力をつけてきました。業界の中にそうした「術(すべ)」や「しくみ」が根付いているのかもしれません。一緒にそれを探っていきましょう!どうぞよろしくお願いいたします。